神世七代について『古事記』にはこのように書いてあります。
次成、神。名國之常立神。次豊雲野神。此二柱神亦獨神成坐而隠身也。
次成、神。名宇比地迩神。次妹洦比智迩神。次角杙神。次妹活杙神。次意富斗能地神。次妹大斗弁神。次於母陀流神。次妹阿夜訶志古泥神。次伊邪那岐神。次伊邪那美神。
上件自國之常立神以下。伊邪那美神以前。并稱神世七代。
国史大系(7)より
今回はここにある国之常立神について解説していきます。
国之常立神とは

国之常立神とは1つ前に生まれた、別天神の天之常立神と対応しています。
国之常立神は『日本書紀』において、「国常立尊」「国底立尊」の名前で第一段の所伝全てに登場しますが対応する天之常立神は一書の六のみに登場します。
なお、国之常立神は第一段本書一書の一、四、五では天地開闢における最初に生まれた神として登場しています。
『古事記』では獨神(性別のない神)とされる国之常立神ですが、『日本書紀』においては陽気のみを受けて生まれて全く陰気を受けない純粋な男神として「純男の神」と記されています。
国之常立神という名前の意味については様々な説があります。
常を恒久、立を留まるとして「国(国土)に恒久に留まるという意味ととって国土の根源神とする説」
ただ、上代語では「常」が動詞を修飾する用法を見出されていないといった指摘があります。
常を床(土台)、立を現れるとして「土台(大地)の出現を表す神名とする説」
これにも指摘があり、神世七世は伊邪那岐神と伊邪那美神の生成過程を表現したものとして捉える立場から大地の形成は岐美二神によって初めてなされるのであって、国之常立神が登場する段階ではまだ大地が形成されていないとされています。
これを踏まえた上でトコタチとは神々や大地、国土が形成されていく土台となる根源的な空間の出現を意味し、国之常立神はそのような「観念的な場の成立を意味する説」
また、これにも上代語のトコは土台ではなく寝たり座ったりする場所のことで、それは男女交合の場や生殖を準備する場として捉えられるといった指摘があります。
よって、神名のトコは土台の意味ではなく生殖および誕生の場といったイメージに基づく神々生成の場を意味すると言われています。
この場合にトコの第一義が「床」だとしても神名には「常」の字が当てられているので、その空間の恒久性は含意されていると考えられています。
国之常立神から伊邪那美神までの神を「神世七世」といいます。
神世七世の存在意義については伊邪那岐神と伊邪那美神の誕生をゴールとして、そこまでの過程を神々の生成によって発展的に表現したものと捉える解釈が多いです。
その過程の意味としては
- 国土の形成を表す説
- 地上の始まりを担う男女神の神体の完成を表す説
- 地上における人類の生活の始原を表す説
などがあります。
伊勢神道における国之常立神は天之御中主神、豊受大神とともに根源神とされています。
伊勢神道の影響を受け、吉田神道では国之常立神と天之御中主神を同一神とし大元尊神(宇宙の根源神)とされています。
さらに教派神道諸派は伊勢神道から吉田神道の流れを汲み、国之常立神を重要な神としています。
神仏分離によって全国各地の妙見社は祭神を天之御中主神に改めましたが、一部では祭神を国之常立神に改めた社もあったそうです。
そこでは国土形成の根源神、国土の守護神として信仰されています。
神社紹介
玉置神社
住所→〒647-1582 奈良県吉野郡十津川村玉置1
公式HP→http://tamakijinja.or.jp/index.html
大鳥神社
住所→〒153-0064 東京都目黒区下目黒3丁目1−2
公式HP→https://www.ootorijinja.or.jp/
日枝神社
住所→〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目10−5
公式HP→https://www.hiejinja.net/index.html
八代神社(妙見宮)
住所→〒866-0802 熊本県八代市妙見町405
公式HP→不明
高椅神社
住所→〒323-0154 栃木県小山市高椅702
公式HP→http://www.tochigi-jinjacho.or.jp/?p=783
さいごに
いかがだったでしょうか?
国之常立神についてだいぶ理解出来たのではないでしょうか。
当サイトではこのような記事の他に御朱印についての記事もあるのでそちらも覗いてみてください。
今回は以上です。
この記事の関する感想などコメントして頂けると私の励みになります。
最後までご覧いただきありがとうございました!
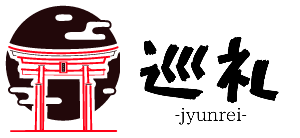



コメント