今回は神世七世の四代にあたる角杙神と活杙神について解説していきます。
この記事はこのような方にオススメの記事となっています。
- 角杙神と活杙神について詳しく知りたい!
- 神世七世について知りたい!
- 角杙神と活杙神が祀られている神社はどこ?
角杙神と活杙神の解説をしていく前に、今回参考にした『古事記』から角杙神と活杙神をはじめとする神世七世について書かれている部分を抜粋して紹介します。
次成、神。名國之常立神。次豊雲野神。此二柱神亦獨神成坐而隠身也。
次成、神。名宇比地迩神。次妹洦比智迩神。次角杙神。次妹活杙神。次意富斗能地神。次妹大斗弁神。次於母陀流神。次妹阿夜訶志古泥神。次伊邪那岐神。次伊邪那美神。
上件自國之常立神以下。伊邪那美神以前。并稱神世七代。
国史大系(7)より
ちなみにここに書いてある「妹」は女神を表しており、男神とは夫婦や兄妹の関係性だとされています。
今回の記事はこちらの文章や『日本書紀』を参考にして書かれています。
角杙神と活杙神とは

まず初めに角杙神と活杙神は角杙神が男神、活杙神が女神として2神で対になる神です。
そのため、この2神には名前やその意味に共通点があります。
ちなみに『日本書紀』では第三段一書のみ登場し、そこではそれぞれ「角樴神」「活樴神」と書かれています。
このことを踏まえた上で読んでください。
角杙神と活杙神はどちらの名前にもあるように杙を表す神です。
その理由についてこれから説明していきます。
説明する上でまずは名前を分けてそれぞれの意味を紐解いていきます。
角杙神の「角」は「葦などの芽立ちを意味する説」と「角のように硬く突起している様を表している説」があります。
この記事では後者の「角のように硬く突起している様を表している説」を採用します。
活杙神の「活」は活きいきとしたという意味で「生命力を象徴」しています。
角杙神と活杙神の両方に共通する「杙」には「地面から植物が生えている様子を表している」と「地面に打ち込む杭を意味する」この2つの意味合いがあります。
これらから角杙神は角のように芽が出始めるといった意味を込めて「角状の杙」を表す神であり、活杙神は芽の生育し始めの意味を込めて「活きいきとした杙」を表し神とされています。
次は角杙神と活杙神や神世七世の意義について説明します。
意義
ここからは角杙神と活杙神や2神を含む神世七世の意義について説明していきます。
神世七世
まず初めに角杙神と活杙神も入っている「神世七世」について解説します。
神世七世とは『古事記』における国之常立神から伊邪那岐神、伊邪那美神までの12柱7代の神を表した総称です。
最初の2代(国之常立神、豊雲野神)は獨神のため1柱1代とし、宇比地邇神と須比智邇神からは男女神2柱を1代として数え合計12柱7代を神世七世と呼びます。
国之常立神と豊雲野神、宇比地邇神と須比智邇神についてはこちらをご覧ください。
宇比地邇神(うひぢにのかみ)と須比智邇神(すひぢにのかみ)とは【神世七世】
神世七世の存在意義としては伊邪那岐神と伊邪那美神の誕生をゴールとして、そこまでの過程を神々の生成によって発展的に表現したものと捉える解釈が多いです。
その過程の意味としては
- 国土の形成を表す説
- 地上の始まりを担う男女神の神体の完成を表す説
などがあります。
この過程における角杙神と活杙神の意義については次で解説します。
角杙神と活杙神
上記にもある通り角杙神と活杙神は共に「杙」を表す神です。
その意義は神世七世の解釈によって変わってきます。
- の場合、宇比地邇神と須比智邇神よって国土が固まったことを受けて角杙神が神の原型となる杭の発生を表し、活杙神がその活動を表している。
- の場合、宇比地邇神と須比智邇神で生じた泥や砂から初めて神の形が発生することを表している。
他には「湿地が固まることにまつわる神説」や「悪霊の侵入を防ぐ防塞神とする説」「杭を依代として降臨する神とする説」などがあります。
これらのことから角杙神と活杙神の神名の意義とは「泥土が固まり、生物が育つことができるようになった」ことを示すことです。
角杙神と活杙神の解説は以上になります。
最後に角杙神と活杙神を祀る神社を紹介して終わります。
神社紹介
物部神社
住所→〒694-0011 島根県大田市川合町川合1545
公式HP→https://www.mononobe-jinja.jp/
宮浦宮
住所→〒899-4501 鹿児島県霧島市福山町福山2437
公式HP→https://www.kagojinjacho.or.jp/shrine-search/area-airaisa/%E9%9C%A7%E5%B3%B6%E5%B8%82/1247/
さいごに
いかがだったでしょうか?
角杙神と活杙神についてだいぶ理解出来たのではないでしょうか。
当サイトではこのような記事の他に御朱印についての記事もあるのでそちらも覗いてみてください。
今回は以上です。
この記事の関する感想などコメントして頂けると私の励みになります。
最後までご覧いただきありがとうございました!
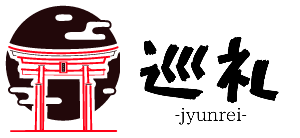



コメント