天之常立神について『古事記』にはこのように書いてあります。
〜前略〜
如葦牙因萠騰之物而成神。
名宇摩志阿斯訶備比古遅神。
次天之常立神。
此二柱神亦獨神成坐而隠身也。
上件五柱神者。別天神。
国史大系(7)より
今回はこの天之常立神についてさらに深掘りしていきます。
最後には神社も紹介しています。
『古事記』の前略部分が気になる人はこちらをご覧ください。
造化三神(ぞうかさんしん)とは【別天神・天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神】
また、この記事はこちらを参考に書いています。
天之常立神とは

天之常立神とは宇摩志阿斯訶備比古遅神の次に生まれた5番目の神で、別天神の中では最後に生まれた神です。
天之常立神のトコタチ部分の意味合いは様々な説があります。
- 高天原に恒久的に留まる神とする説
- 大地の出現を表す神とする説
- 観念的な場の成立を意味する説
代表的なのはこの3つです。
この3つについて反対意見も含めて解説します。
まず、「高天原に恒久的に留まる神とする説」について
これは常=恒久、立=留まるの意味からきている説ですが、これには常が動詞を修飾していないという反対意見があります。
次に「大地の出現を表す神とする説」について
これは常=床(大地)、立=現れるの意味からきている説ですが、大地の形成はイザナギとイザナミによって初めてなされるので天之常立神が生まれる頃はまだ大地が出現する段階ではないという意見もあります。
最後に「観念的な場の成立を意味する説」について
この説は常立とは神々や大地、国土が生成されるための土台となる根源的な空間を意味するという見解からきている説となっており、「大地の出現を表す神とする説」が元となっている説です。
これにはトコとは土台ではなく寝たり座ったりする場所のことで、男女交合の場や生殖を準備する場として捉えられるといった指摘があったり、生殖や誕生の場というイメージに基づく神々の生成の場を意味するといった意見があります。
ですが、トコの定義が床だとしても名前に常の字が当てられていることでその空間の恒久性は含意されているとされています。
また、『新撰姓氏録』左京神別下において伊勢朝臣の祖神として天日別命を孫とする「天底立命」が登場します。
この天底立命と天之常立神は同一神とされています。
天之常立神といった名前は次に生まれる国之常立神と対応していますがこの2柱の関係性には少し問題があります。
『古事記』においては天之常立神が別天神で国之常立神が神世七代です。
別天神は天上の事柄にのみ関わる神とし、神世七代は国土に関わる神といった違いがあります。
これにも「別天神が天上にのみ関わる説」と「造化三神が天上のみに関わり後2柱は天上と国土の両方に関わる説」がありますがどちらが正しいかはわかりません。
別天神(ことあまつかみ)とは【天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神・宇摩志阿斯訶備比古遅神・天之常立神・造化三神】
造化三神(ぞうかさんしん)とは【別天神・天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神】
『日本書紀』においては天之常立神は一書第六にしか登場しませんが、国之常立神は七つの伝全てに登場します。
このことから天之常立神は国之常立神に相対する神として創り出された後出の神とする説があります。
このように天之常立神と国之常立神は関係しています。
獨神成坐而隠身也。
この一文から天之常立神が獨神であることがわかります。
獨神とは男女の性別がない神のことです。
上件五柱神者。別天神。
この五柱とは造化三神(天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神)、宇摩志阿斯訶備比古遅神、天之常立神の5柱のことです。
この5柱をまとめて別天神と呼びます。
高御産巣日神(たかみむすひのかみ)とは【別天神・造化三神・八神殿】
神産巣日神(かみむすひのかみ)とは【別天神・造化三神・八神殿】
神社紹介
駒形神社
住所→〒023-0000 岩手県奥州市水沢中上野町1−83
公式HP→http://komagata.iwate.jp/
金持神社
住所→〒689-4512 鳥取県日野郡日野町金持1490
公式HP→https://kanemochi-jinja.net/
さいごに
いかがだったでしょうか?
天之常立神についてだいぶ理解出来たのではないでしょうか。
当サイトではこのような記事の他に御朱印についての記事もあるのでそちらも覗いてみてください。
今回は以上です。
この記事の関する感想などコメントして頂けると私の励みになります。
最後までご覧いただきありがとうございました!
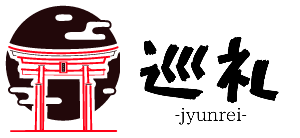



コメント