一人暮らしを始めたり、新しく家を買った人は神棚を祀る場所やお神札の祀り方を知らない人がほとんどです。
なのでこの記事では神棚を祀る場所やお神札の祀り方について簡単に説明します。
もし、役に立ったら感想などコメントして頂けると嬉しいです。
こちらの記事では神棚の起源について触れています。
祀る場所について
神棚とはお札を祀るとても神聖な場所です。
そのため、神棚は家の中で最も清潔な場所に祀るのが良いでしょう。
その上で人がよく集まり賑やかなところが良いとされています。
自宅の場合はリビング、会社の場合はオフィスなどに神棚を祀る人が多いです。
ただし、神棚の上下を通り抜けれる場所(部屋の出入り口や階段の下)、二階の水回りや廊下の下は避けてください。
今、説明したことは神棚を祀る上での最低条件です。
神棚を祀る上で適した方角や場所、逆に適さない方角や場所があるので、これからその方角や場所について説明します。
適した方角と場所

神棚には祀るのに適した方角や場所があります。
神棚は「東向きか南向き」に祀ると良いとされています。
これにはちゃんとした理由があります。
東は1日に始まりである朝日が昇ってくる方角であり、南は1日の中で一番高くなる方角です。
このことから東は活力や成長、南は充実や繁栄を象徴する方角と言われています。
これらの陽の光を神棚に当てるために神棚の向きは「東向きか南向き」が良いとされています。
また、「背山面水」の地形も良いとされています。
背後に山があって正面に平野や盆地といった開けた地形のことを言います。
風水ではこのような地形は方角に関係なく吉であるという考え方があります。
「東向きか南向き」や「背山面水」以外だと縁起が悪いわけではありません。
ちょうど良い場所がない場合は家の中にある清潔でお参りしやすいところに祀れば大丈夫です。
適さない方角と場所
逆に神棚を祀るのに適していない方角や場所も存在します。
<適した方角と場所>の最後でも書きましたが西向きや北向きだと縁起が悪いわけではありません。
なので今回は適さない場所をいくつか紹介します。
まずは「仏壇と向かい合いになる場所」です。
これはどちらかに手を合わせている場合、もう一方に背中を向けてしまうのでよくありません。
次に「神棚の上下を通り抜けれる場所」です。
これは部屋の出入り口や階段の下などのことを言います。
二階の廊下の下も避けなくてはいけませんが、マンションやアパートの場合は一戸が1つの家屋と考えてください。
どうしての気になる方は神棚の上に”雲””天””空”といった墨書を貼ると良いでしょう。
汚れやすい「キッチンや台所」も避けた方が良いです。
ですが、間取りなどの理由によりキッチンや台所にしか祀れない場合もあると思います。
その場合は火を祀る神様である荒神様も一緒に祀ることで解決できるそうです。
神棚を祀る上での適した方角や場所、逆に適さない方角や場所については以上です。
次は神棚に祀るお神札について説明します。
お神札の配置
お神札にも正式な配置があります。
お神札は基本的に3列にして祀ります。
お神札を祀る順位として、中央→右→左の順に神様の位が高くなっています。
ですが、三社造(扉が3つ)と一社造(扉が1つ)ではお神札の祀り方が少し違ってきます。
三社造では中央に日本の総氏神様である伊勢神宮のお神札(神宮大麻)、右に地元の氏神様のお神札、左に崇敬している神社のお神札を祀ります。
崇敬する神社のお神札が複数ある場合は左側に重ねて祀りましょう。
一社造では扉が1つしか無いため、全てのお神札を重ねて祀ります。
一番手前に神宮大麻、次に地元の氏神様、次に崇敬する神社の順に重ねて祀ります。
崇敬する神社のお神札が複数ある場合は後ろに重ねて祀りましょう。
お神札が多くなって神棚に収まらなくなったり、神棚に入らない大きさのお神札は神棚の横へ丁寧に並べて祀ります。
年末の大掃除のタイミングで神棚のお神札も片付けましょう。
大晦日から1月15日の間に神社でお焚き上げをして、新しいお神札を神棚に祀ってください。
さいごに
いかがだったでしょうか?
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございます。
この記事に関する感想などコメントして頂けると嬉しいです。
最後に今回参考にしたサイトのURLを貼っておくので飛んでみてください。
神棚奉斎・まつり方 https://hokkaidojinjacho.jp/ritual-dwelling/qa-01/
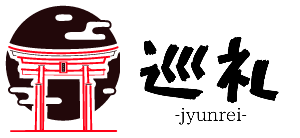

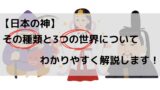
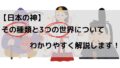

コメント