日本には「八百万の神々」と言われるほど神が多いです。
今回は神の種類と神々が住む3つの世界について簡単にわかりやすく解説していきます。
先に言っておきますと細かい説明はしていません。
「簡単にわかりやすく」に重きを置いて解説していきます。
この記事はこちらの本を参考に書かれています。
神の種類

日本で言う”神”はとても複雑です。
キリスト教の”神”を想像する人もいれば、神と仏を一緒くたにする人もいます。
そこで元々はどのような存在が”神”と呼ばれているのか、大きく3つに分けるとこうなります。
- 「古事記」「日本書紀」「風土記」などの神話に登場する”神”
- 神話には登場しないが民間神や民族神と呼ばれる”神”
- 元は人間で死後、神になった”神”
この3種類の神についてもう少し詳しく説明していきます。
神話に登場する”神”
神話には大地を創造した神やヒーローのような活躍をした神などが登場します。
神話に登場する神の中でも、人間のように怒ったり笑ったり結婚したりする神を”人間神”といい、山や海といった自然そのものの神を”自然神”といいます。
さらに人間神には高天原に住む”天つ神”と葦原中国に住む”国つ神”がいます。
有名な神で言うと天照大御神は天つ神、大国主神は国つ神です。
高天原や葦原中国については後ほど説明します。
神社に祀られている神の多くが天つ神や国つ神といった人間神ですが、自然神も同時に祀っている神社もあります。
神話には登場しない”神”
神話には登場していませんが民間神や民族神と呼ばれる神もいます。
有名なのは稲荷神や恵比寿などが”民間神”です。
人々の間で自然発生的に生まれた神で始まりがはっきりとしないことが多いです。
この神は神話に登場する神と結び付けられて神社に祀られることがあります。
元は人間だった”神”
神話や自然発生した神ではなく、生きていた人間が死後に神になることもあります。
有名なのは天満宮に祀られる天神さま(菅原道真)や東照宮に祀られる東照宮権現(徳川家康)です。
元は恨みを持って亡くなった人の祟りを鎮めるために神として祀ったことに始まります。
その後、徳川家康のように優れた人間も神として祀るようになりました。
神社の名前による違いはこちらに書いています。
次は今紹介した神々が住む世界について説明します。
神々の住む世界
<神話に登場する”神”>のところで少し紹介しましたが、神といっても全ての神が同じ世界に住んでいる訳ではありません。
これから説明する世界をざっくりと書くとこんな風になります。
- 天照大御神が統治する高天原
- 大国主神が統治していた葦原中国
- 死者のいる黄泉の国(根の国)
ここではこの3つの世界を世界別に詳しく説明していきます。
高天原たかまがはら
高天原とは天照大御神が統治する天上界の名称です。
この高天原に住む神々のことを総して”天つ神”と呼びます。
高天原には大国主神に大地の統治権を譲るように交渉した”建御雷神”や邇邇芸命が葦原中国に降ったときお供した”天手力男神””天宇受売命”などがいます。
統治している天照大御神とは伊邪那岐命が黄泉の国から戻ったときに行った穢れを落とす禊により生まれた女神のことで、皇室の祖神でもあります。
葦原中国あしはらのなかつくに
葦原中国とは大国主神が作り、統治していた地上界です。
この葦原中国に住む神々のことを総じて”国つ神”と呼びます。
私たち人間がいるのも葦原中国です。
葦原中国には高天原から大地へ降る神々の先導役を務めた”猿田毘古神”や大国主神の子である”事代主神””建御名方神”などがいます。
葦原中国は大国主神が作り統治していましたが、あるとき天照大御神は「葦原中国は自分の子が統治すべき」と考えました。
そこで天つ神である建御雷神が大国主神に国を譲るように交渉しました。
交渉の末、大国主神に代わり天照大御神の孫である邇邇芸命が葦原中国を統治するようになりました。
これが「国譲り」と呼ばれている神話です。
黄泉の国(根の国)
今回は黄泉の国と根の国を同一のものとして紹介します。
黄泉の国(根の国)は死者のいる国です。
黄泉の国(根の国)と葦原中国は黄泉平坂で繋がっており、2つの世界は”千引の岩”と呼ばれる巨岩で隔てられているとされています。
黄泉の国(根の国)には死後の”伊邪那美命”や「古事記」後半の”須佐之男命”などがいます。
伊邪那岐命は死んだ伊邪那美命を連れ戻そうと黄泉の国(根の国)へ行った帰りに黄泉の穢れを落とす禊を行いました。
全身水に入り身を清めたところで左目を洗うと”天照大御神”右目を洗うと”月詠命”鼻を洗うと”須佐之男命”が生まれたとされています。
神社の始まり
古代の日本では「神は祭祀のときに降ってきて終わると去っていく」とされていました。
そのため、特定の場所に常在する社殿はありませんでした。
また、神は自然のものに降るとされていて山や木、岩などを依代にし臨時の祭場を作って祭祀を行っていました。
福岡県沖ノ島の遺跡群や奈良の三輪山には4世紀頃に祭りをやった痕跡が残っています。
6世紀になると日本に仏教が伝わってきます。
伝わってきた仏教には仏像があり、祈りと修行の場である寺院がありました。
このことは神が常在する社殿を作っていない日本に大きな影響を与ました。
奈良時代から神社に社殿を造営する習慣があると確認されています。
これが神社の始まりです。
家ある神社「神棚」
神棚が普及したのは江戸時代中期だと言われています。
この時、伊勢神宮や富士山へお参りに行くことが流行っていました。
これをガイド知る人たちが進行を普及するために考えた”大宮司棚”が神棚の元となったとされています。
神棚は伊勢神宮の社殿を模した神明造りが一般的で、扉が1枚のものと3枚のものがあります。
初詣などでいただく神札は基本的にそれぞれの神が管轄する場所に備えますが、近世以降は神棚に備える方法も普及しています。
さいごに
今回は日本の”神”と神々が住んでいる世界について解説しました。
私もこの記事を書くまで知らなかったことがありました。
こういった豆知識以外にも自分で行った神社についてなど書いているので良かったら覗いてみてください。
今回は以上です。
この記事に関する感想などコメントして頂けると嬉しいです。
この記事はこちらの本を参考にしています。
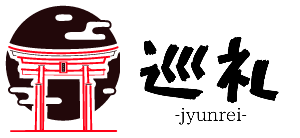
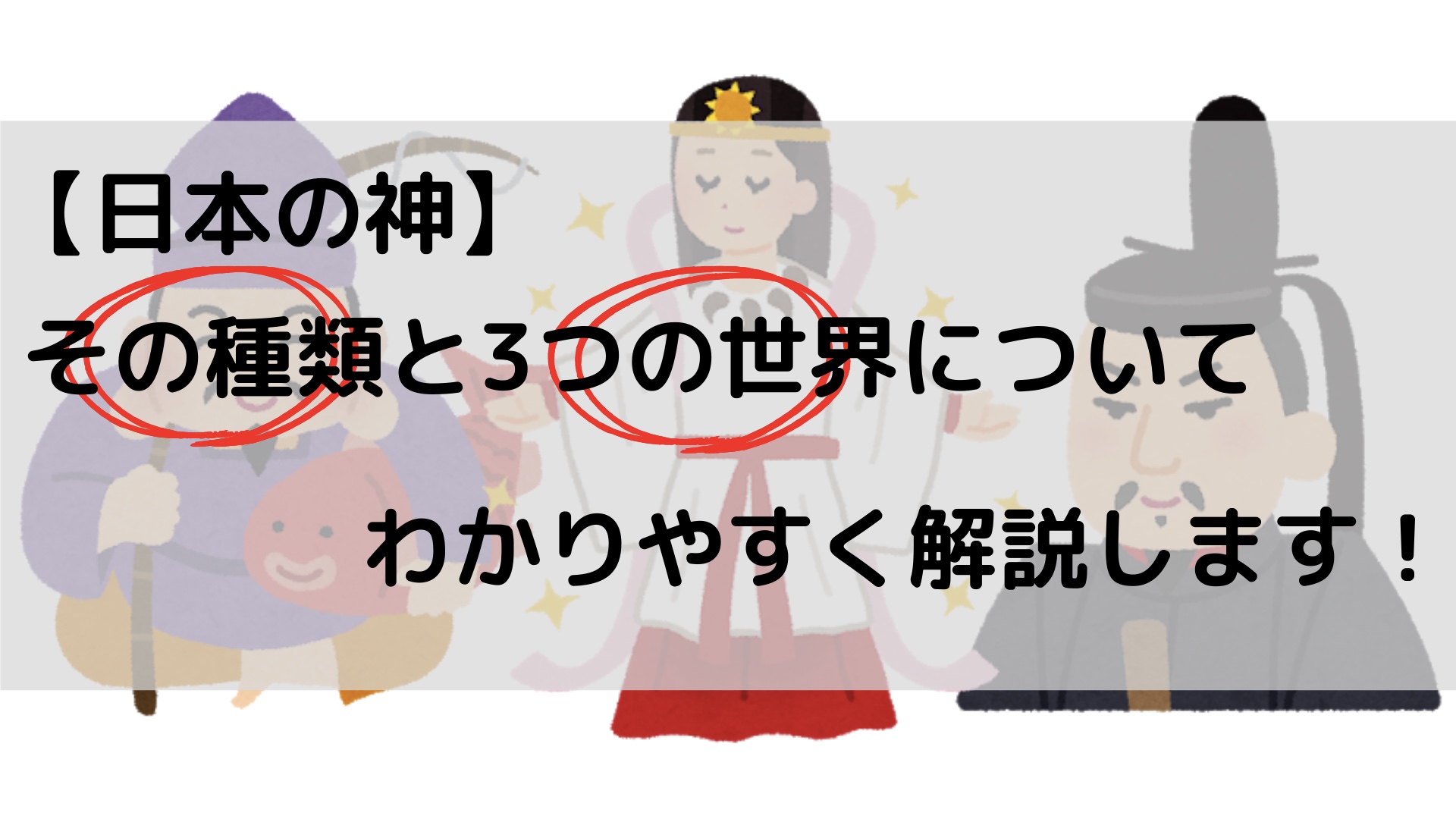

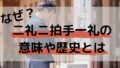

コメント