今回は神社を調べる中で度々出てくる「延喜式」「式内社」について簡単に解説していきます。
細かく説明する前に大きくまとめるとこうなっています。
- 延喜式とは古代法典のこと
- 延喜式神名帳とは延喜式の9、10巻のこと
- 式内社とは延喜式神名帳に書かれている神社のこと
これからこのことについて細かく解説していくのでぜひ最後までご覧ください。
延喜式とは

延喜式とは「養老律令」をもとに延喜5年(905年)に藤原時平を含めた12名の委員によって作られ始めた古代法典のことです。
延長5年(927年)には藤原忠平など5名が天皇に献上しました。
その後も修正が加えられ、40年後の康保4年(967年)に施行されました。
延喜式は全50巻あり、1〜10巻が神祇官関係の式、11〜40巻が太政官八省関係の式、41〜49巻がその他の官司関係の式、50巻が雑式となっていて律令官制に従って配列されています。
その中で9巻10巻は延喜式神名帳と言われていて、そこに書いてある神社のことを延喜式内社や式内社と言い一種の社格となっています。
神社を調べる上で度々出てくる「延喜式に書いてある」という言葉は「延喜式神名帳に書いてある式内社である」という意味で使われていると思います。
三代格式(弘仁格式、貞観格式、延喜格式)のなかで今日までほぼ完全な形で伝えられているのは延喜式だけだそうです。
式内社
先ほども書いたように式内社とは「延喜式の9、10巻に書いてある神社」のことです。
式内社は全国に2861社あり、そこに鎮座する神様の数は3132座にも及びます。
その式内社の中にも官幣社と国幣社の2種類に分かれ、さらにそれぞれに大社と小社に分かれます。
それぞれの神社、神様の数はこのようになっています。
| 名前 | 神社の数 | 神様の数 |
| 官幣大社 | 198社 | 304座 |
| 官幣小社 | 375社 | 433座 |
| 国幣大社 | 155社 | 188座 |
| 国幣小社 | 2133社 | 2207座 |
この内、官幣大社は畿内(都や皇居に近い地域≠首都圏)に集中していて官幣小社は全て畿内に建てられています。
国幣社は大社、小社ともに畿外に建てられています。
また、延喜式が作られた時にも数多くの神社がありましたがあらゆる理由があり延喜式には記載されていない神社があります。
その神社のことを式外社と言います。
今まで訪れた式内神社
成海神社の記事はこちらから
熱田神宮摂社、氷上姉子神社の記事はこちらから
針名神社の記事はこちらから
さいごに
短いですが今回は以上になります。
延喜式については理解出来ましたでしょうか?
これでさらに神社を見る楽しみが増えたと思います。
この記事に関する感想などコメントして頂けると嬉しいです。
今回参考にしたサイトはこちらです。
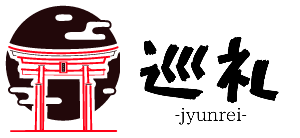


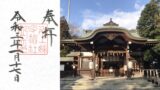



コメント