天之御中主神について『古事記』には
天地初發之時於高天原成神。名天之御中主神。
次高御産巣日神。次神産巣日神。三柱神者。並
獨神成坐而隠身也。
〜中略〜
上件五柱神者。別天神。
国史大系(7)より
とだけしかありません。
そんな天之御中主神をこれから深掘りしていきます。
現代文に直しつつ解説していくので最後までご覧ください。
別天神(ことあまつかみ)とは【天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神・宇摩志阿斯訶備比古遅神・天之常立神・造化三神】
天之御中主神(あめのみなかぬし)とは

そもそも天之御中主とはどういった意味なのか。
天之御中主とは「天の中心」といった意味があります。
これは古事記の
天地初發之時於高天原成神。
から最初に誕生した神が由来になっています。
また、最初に誕生した神から宇宙の根源の神とも言われています。
同じく天の中心である妙見菩薩と同一神とされることもあります。
*天の中心にいる神霊とされる北斗七星、北極星を神格化した妙見菩薩と天の中心という意味の天之御中主神が神仏習合された。
獨神成坐而
これは天之御中主神が獨神、つまりは男女の性別がない神だということを言っています。
獨神は他にも高御産日神、神産日神、宇摩志阿斯訶備比古遅神、天之常立神がいます。
高御産巣日神(たかみむすひのかみ)とは【別天神・造化三神・八神殿】
神産巣日神(かみむすひのかみ)とは【別天神・造化三神・八神殿】
宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひごじのかみ)とは【別天神】
最初に生まれた獨神5柱あるいは3柱を「別天神」や「造化三神」と呼びます。
別天神(ことあまつかみ)とは【天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神・宇摩志阿斯訶備比古遅神・天之常立神・造化三神】
造化三神(ぞうかさんしん)とは【別天神・天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神】
隠身也。
これは身を隠してしまったという意味です。
天之御中主神は冒頭の3行ほどで隠れてしまい、それ以降出てくることはありません。
これだけ登場が短い天之御中主神ですが、全国の水天宮をはじめ多くの神社で祀られています。
次は天之御中主神を祀る神社の系統について解説します。
神社の系統について

天之御中主神を祀る神社には妙見系、水天宮、大教院・教派神道系の3系統があります。
現在ある天之御中主神を祀る神社の多くは妙見社が神仏分離によって、天之御中主神を祭神として祀り始めたところがほとんどです。
また、天之御中主神が祭神の神社は「延喜式」には記載されていません。
【それってなに?!】延喜式や式内社、延喜式神名帳とは一体何?わかりやすく簡単に解説します!
妙見社系
妙見社系のもとを辿れば道教における天皇大帝信仰にあります。
上記にもあるように北斗七星・北極星信仰、仏教の妙見信仰が神仏習合のより天之御中主神信仰と習合されました。
これがきっかけとなり、天之御中主神を祀るようになった妙見社のことを妙見社系と呼んでいます。
例えば、千葉県にある妙見本宮千葉神社や埼玉県にある秩父神社、岩手県にある九戸神社などが妙見社系とされています。
水天宮
元々、水天宮と天之御中主神は無関係でしたが明治維新の神仏分離によって祭神に追加されました。
そのため、福岡県にある総本宮水天宮をはじめ全国にある全ての水天宮では天之御中主神を祭神として祀っています。
大教院・教派神道系
大教院・教派神道系では明治初期に祭神とされ、いくつかの神社も祭神に加えています。
例えば、東京都千代田区にある東京大神宮や長野県にある四柱神社などが大教院・教派神道系とされています。
代表的な神社
先ほど例にあげたいくつかの神社のマップと公式HPを貼っておくので参考にしてください。
妙見本宮千葉神社
住所→〒260-0018 千葉県千葉市中央区院内1丁目16−1
公式HP→https://www.chibajinja.com/
秩父神社
住所→〒368-0041 埼玉県秩父市番場町1−3
公式HP→http://www.chichibu-jinja.or.jp/
九戸神社
住所→〒028-6504 岩手県九戸郡九戸村長興寺第1地割10
公式HP→http://www.vill.kunohe.iwate.jp/docs/233.html
総本宮水天宮
住所→〒830-0025 福岡県久留米市瀬下町265
公式HP→http://suitengu.net/
東京大神宮
住所→〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4−1
公式HP→http://www.tokyodaijingu.or.jp/
四柱神社
住所→〒390-0874 長野県松本市大手3丁目3−20
公式HP→https://www.go.tvm.ne.jp/~yohasira/
さいごに
いかがだったでしょうか?
天之御中主神についてだいぶ理解出来たのではないでしょうか。
当サイトではこのような記事の他に御朱印についての記事もあるのでそちらも覗いてみてください。
今回は以上です。
この記事の関する感想などコメントして頂けると私の励みになります。
最後までご覧いただきありがとうございました!
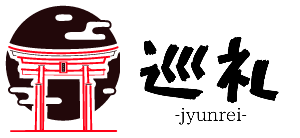



コメント